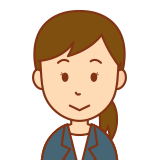
在宅介護のお風呂が不安。
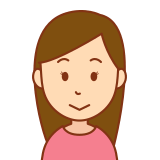
どうやって安全に入れる?
毎日の入浴介助は体力的にも精神的にも大きな負担になりますね。
適切な知識や準備なしに行うと、思わぬ事故につながるかもしれません。
そこで、今回は在宅介護での負担を減らすお風呂介助のコツと便利なグッズについて紹介します!
- 安全な入浴方法
- 腰痛予防のコツ
- 時短テクニック
目次
在宅介護でのお風呂介助に必要な5つの準備

在宅介護でのお風呂介助を安全に行うためには、事前の準備が何よりも大切です。特に親御さんの身体状況に合わせた入念な準備をしておくことで、介護する側もされる側も安心して入浴時間を過ごすことができます。
では、具体的にどのような準備が必要なのでしょうか。
これら5つの準備をしっかりと行うことで、在宅介護のお風呂介助における多くのトラブルを未然に防ぐことができます。介護は長期戦となるため、最初から正しい方法で行うことがとても重要です。
それでは、それぞれの準備について詳しく見ていきましょう。
入浴前の健康チェック
お風呂に入る前に、必ず健康状態の確認をしましょう。
入浴は体に大きな負担をかける行為であり、特に高齢者にとっては血圧の急激な変化を引き起こす可能性があります。
日々の健康状態を把握しておくことで、その日の体調に合わせた入浴方法を選択することができるのです。
まず、血圧や体温などのバイタルサインを測定します。
目安として、収縮期血圧が180mmHg以上、または拡張期血圧が100mmHg以上の場合は入浴を見合わせたほうが安全です。また、体温が37.5度以上ある場合も同様に注意が必要です。
次に、その日の体調や気分についても確認しましょう。
「今日は少し疲れている」
「めまいがする」などの訴えがある場合は、無理せず清拭やシャワー浴に切り替えることも検討してください。
食事との関係も重要です。
食後すぐの入浴は消化器官に血液が集中している状態で入浴することになり、心臓に負担をかけます。食後1時間程度経ってから入浴するのが理想的です。
逆に、空腹時の入浴も低血糖を引き起こす恐れがあるため避けましょう。
持病のある方は、服薬のタイミングと入浴のタイミングも考慮する必要があります。
降圧剤を服用している場合は、入浴によって血圧がさらに下がることがあるため、かかりつけ医に相談の上、適切な時間帯を選びましょう。
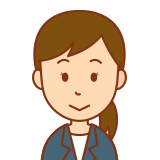
毎日のちょっとした変化を見逃さないことが大切ね
お風呂の温度調整
入浴環境の温度管理は命に関わる重要事項です。
高齢者は温度変化に弱く、体温調節機能も低下しています。適切な温度設定をすることで、ヒートショックを防ぎ、安全に入浴を楽しむことができるのです。
まず、浴室内の温度は冬場でも24度前後に保つようにしましょう。
入浴前に浴室を暖めておくことで、脱衣所から浴室への移動時の温度差を最小限に抑えることができます。脱衣所も同様に暖かくしておき、温度差による血圧の急激な変動を防ぎます。
湯温は38度から40度の間が理想的です。熱すぎるお湯は血圧を上昇させ、心臓に負担をかけます。
逆に、ぬるすぎると体が冷えてしまいます。必ず湯温計を使用して、正確な温度を確認してください。
季節や気温によっても適切な温度は変わります。
夏場はやや低め(38度前後)、冬場はやや高め(40度前後)に設定するとよいでしょう。ただし、個人によって好みの温度は異なるため、被介護者の方の意見も聞きながら調整することが大切です。
浴室と脱衣所の温度差が大きいと、血圧の急激な変動を引き起こし、ヒートショックの原因となります。
特に冬場は注意が必要で、脱衣所にヒーターを設置するなどの対策を講じることをおすすめします。
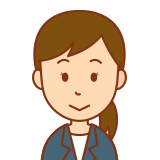
浴室と脱衣所の温度差に気をつけないとね
必要な道具を揃える
効率的な入浴介助には適切な道具が欠かせません。
必要な道具を事前に準備しておくことで、入浴中に慌てることなく安全に介助を行うことができます。また、介護者の負担を軽減する工夫も重要です。
まず基本的な入浴用品として、介護用のボディーソープやシャンプー、コンディショナーを用意しましょう。
介護用の洗髪剤はすすぎが簡単で、頭皮に優しい成分のものが多く販売されています。また、泡タイプのボディーソープは素早く洗えるため、入浴時間の短縮につながります。
洗体用のスポンジやタオルは、柔らかく肌への刺激が少ないものを選びましょう。
特に、長柄のスポンジは介護者の腕の届きにくい背中などを洗うのに便利です。同様に、シャンプーハットも髪の長い方の洗髪時には重宝します。
体を拭くタオルは複数用意しておくと安心です。
大判のバスタオルだけでなく、ハンドタオルもいくつか準備しておくと、部分的に拭いたり、髪を拭いたりするのに便利です。使い捨てのおしぼりタイプの商品も、緊急時や外出先での清拭に役立ちます。
着替えも忘れずに準備しておきましょう。
下着、パジャマや部屋着、靴下など、着る順番に並べておくと慌てずに済みます。着脱しやすい前開きタイプの衣類を選ぶと、介助がしやすくなります。
その他、タオルケットや浴用介護ワンピースなどがあると、脱衣時や着衣時の恥ずかしさを軽減することができます。プライバシーへの配慮も大切な準備の一つです。
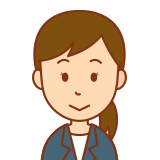
道具をしっかり揃えておくと本当に助かるわ
安全な環境づくり
転倒事故の多くはお風呂場で起こります。
浴室は水や石けんで滑りやすく、高温多湿で体調も変化しやすい危険な場所です。安全に入浴するためには、浴室内の環境整備が欠かせません。
まず、浴室の床にはすべり止めマットを敷きましょう。
浴槽の出入りする場所や立ち位置に特に注意して設置します。すべり止めマットは定期的に裏面を洗浄し、吸着力が低下していないかチェックすることも大切です。
手すりの設置も非常に重要です。
浴槽の縁、浴室の壁、洗い場など、立ち上がったり体を支えたりする場所に適切に設置しましょう。
最近では工事不要で取り付けられる吸盤式の手すりも多く販売されていますが、定期的に吸着力を確認し、必要に応じて専門業者による固定式の手すり設置も検討しましょう。
浴室内の物の配置も見直しましょう。
洗面器やシャンプーボトルなどは手の届きやすい位置に置き、動線をすっきりさせることが大切です。
また、シャンプーとボディソープは形や色が異なるものを選ぶと、視力が低下している方でも識別しやすくなります。
照明も適切な明るさを確保しましょう。
暗いと段差が見えにくくなり、転倒のリスクが高まります。防水タイプの明るいLED照明に交換するだけでも、浴室内の安全性は大きく向上します。
最後に、浴室と脱衣所の段差にも注意が必要です。
段差が大きい場合は、踏み台を置くなどの工夫をしましょう。どうしても改善できない場合は、介助者がしっかりとサポートする必要があります。
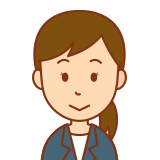
手すり一つで安心感が全然違うわね
介助者の体調管理
介護する側の健康管理も同様に重要です。
介護者自身が体調を崩してしまっては、適切な介助が行えないだけでなく、最悪の場合は二次災害を引き起こす可能性もあります。長く続ける介護のためにも、自分自身のケアを怠らないようにしましょう。
まず、入浴介助を行う前には自分自身の体調チェックを行いましょう。
疲労がたまっている、体調が優れないと感じる場合は、無理せず他の家族に協力を求めるか、訪問入浴サービスの利用を検討することも大切です。
入浴介助は体力を使う作業です。
特に浴槽への出入りの際には腰に大きな負担がかかります。
正しい姿勢で介助を行うことが重要で、膝を曲げて腰を低くし、背筋を伸ばした状態で力を入れるようにしましょう。
また、日頃から腰痛予防のためのストレッチや適度な運動を心がけることも効果的です。
高温多湿の浴室内で長時間過ごすと、介護者自身も熱中症のリスクがあります。
特に夏場は水分補給を忘れずに行い、定期的に涼しい場所で休憩を取りましょう。介助の合間に冷たいタオルで首筋を冷やすなどの工夫も効果的です。
また、介護ストレスを溜め込まないことも重要です。
入浴介助は体力的にも精神的にも負担の大きい作業です。自分の限界を知り、必要に応じてレスパイトケア(介護者の休息のための一時的なケア)を利用することも検討しましょう。
地域包括支援センターや市区町村の介護相談窓口に相談すると、様々なサービスや支援制度を紹介してもらえます。
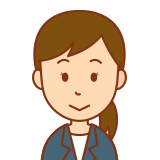
介護者自身も休息が必要よね
在宅介護のお風呂介助の正しい手順と3つのコツ

在宅介護でのお風呂介助を安全かつ効率的に行うためには、正しい手順とコツを知ることが大切です。適切な方法で行えば、介護される方の負担も軽減でき、介護する側も無理なく続けることができます。
では、お風呂介助の基本的な流れと重要なポイントを確認しましょう。
これらのポイントを押さえることで、お風呂介助の質が大きく向上します。特に初めて介護を行う方は、基本をしっかり学んでから実践することで、安全に介助を行うことができます。
それでは、具体的な方法について詳しく見ていきましょう。
衣服の脱ぎ方と着せ方
着替えは入浴の始まりと終わりを決める重要なステップです。
衣服の着脱を安全かつスムーズに行うことで、入浴の負担を軽減できます。また、この過程での転倒予防やプライバシーへの配慮も欠かせません。
まず、脱衣所の温度を事前に調整しておきましょう。冬場は特に低体温のリスクがあるため、脱衣所を暖かくしておくことが大切です。
必要に応じて暖房器具を使用し、室温を22度から25度程度に保ちます。
衣服を脱ぐ順番は、「上から下へ」が基本です。
まず上着を脱がせ、次にズボンや下着と進みます。
この時、麻痺や関節の動きに制限がある場合は、動きやすい側から脱がせ始めるのがポイントです。
例えば、右半身に麻痺がある場合は、まず左側の袖から脱がせ、次に頭を通し、最後に右側の袖を脱がせるという流れになります。
脱衣時の姿勢も重要です。
立位が安定している場合は立ったまま行いますが、ふらつきがある場合は椅子に座ってもらい、転倒のリスクを減らしましょう。
また、プライバシーを守るため、バスタオルで体を覆いながら下着を脱がせるなどの配慮も必要です。
入浴後の着衣は、脱衣の逆の手順で行います。まず下着から着せ始め、上着、ズボンの順に進めます。
この時も動きに制限がある側を先に通すのがコツです。衣服は前開きタイプのものを選ぶと、着せやすく負担が少なくなります。
冬場は特に素早く着衣することが大切です。
体が冷えないよう、バスタオルでしっかり水分を拭き取ってから着衣を始めましょう。
また、着替えをする際に転倒する危険性もあるため、必要に応じて手すりを設置したり、介助者がしっかりと支えたりすることも重要です。
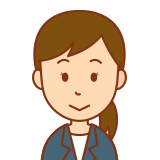
前開きの服は着せやすくて助かるわ
浴室への移動方法
移動時の転倒は介護現場で最も多い事故の一つです。
特に滑りやすい浴室への移動は細心の注意が必要です。安全な移動方法を習得することで、お互いの不安も軽減され、入浴介助がよりスムーズになります。
まず、移動経路に障害物がないか確認しましょう。脱衣所から浴室までの通路に物が置かれていないか、段差はないか、床が濡れて滑りやすくなっていないかなど、事前のチェックが重要です。
歩行に不安がある場合は、歩行器や杖を使用するのも一つの方法です。
ただし、浴室内は湿気が多いため、屋外用の歩行補助具をそのまま使用するのは避け、浴室用の手すりやシャワーチェアを活用しましょう。
介助者がサポートする場合は、正しい介助方法を身につけることが大切です。
基本的な介助姿勢は、被介護者の麻痺がある側や弱い側に立ち、腰を低くして支えます。この時、被介護者の腰や脇の下を支えるのが適切です。
無理に引っ張ったり押したりすると、お互いにバランスを崩す原因になります。
浴槽への出入りは特に注意が必要です。浴槽の縁に腰掛けてから、ゆっくりと浴槽内に足を入れる方法が安全です。
この時、手すりがあれば積極的に活用しましょう。自力での移動が難しい場合は、シャワーチェアや入浴用リフトなどの福祉用具の利用も検討してください。
移動の際は、常に声かけを行うことも重要です。
「次は右足を動かしますよ」
「ゆっくり立ち上がりましょう」
など、動作の前に声をかけることで、被介護者も心の準備ができ、協力して移動することができます。
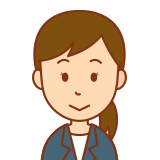
声かけが安心感につながるのよね
体の洗い方の順番
体を洗う順番にも効率的な方法があります。
正しい順序で体を洗うことで、清潔さを保ちながら効率よく入浴介助を行うことができます。また、皮膚トラブルの早期発見にもつながる重要なプロセスです。
まず、洗い始める前に全身をお湯で軽く流し、体を温めましょう。これにより血行が促進され、汚れも落ちやすくなります。
特に冬場は、体を温めてから洗い始めることで、急激な温度変化による体への負担を軽減することができます。
洗う順番は一般的に「清潔な部分から汚れやすい部分へ」が原則です。
具体的には、顔→首→腕→胸・背中→お腹→足→陰部という流れが効率的です。
石けんやボディソープは泡立てネットを使ってしっかり泡立て、直接肌にこすりつけるのではなく、泡で優しく洗うようにしましょう。
顔を洗う際は、目や口に石けんが入らないよう注意が必要です。
シャンプーは体を洗った後に行い、すすぎ残しがないようしっかりとすすぎます。髪が長い場合は、コンディショナーも使用すると、髪の絡まりを防ぎ、乾かす際の負担も軽減されます。
皮膚の観察も忘れずに行いましょう。入浴時は全身の状態を確認できる貴重な機会です。
発赤、傷、褥瘡(床ずれ)の兆候などがないか注意深く観察します。特に、普段見えない背中や臀部、足の裏などは重点的にチェックしましょう。
気になる変化があれば、早めに医療専門家に相談することが大切です。
洗い終わったら、しっかりとすすぎを行います。石けんが残っていると、肌荒れの原因になります。
特に、首の後ろ、脇の下、ひざの裏、股関節の付け根など、すすぎ残しが起こりやすい部分は念入りにすすぎましょう。
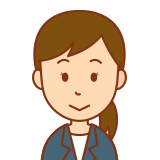
肌のチェックもできる大事な機会なのね
安全な入浴姿勢
正しい姿勢は安全と快適さの両方に直結します。
浴槽内での安定した姿勢は転倒防止につながるだけでなく、介護する側の負担も大きく軽減します。それぞれの身体状況に合った入浴姿勢を工夫しましょう。
まず、洗体時の基本姿勢としては、シャワーチェアに腰掛けた状態が最も安全です。
背もたれのあるタイプを選ぶと、さらに安定感が増します。この時、足がしっかり床につく高さに調整することがポイントです。
姿勢が不安定だと感じる場合は、滑り止めマットの上にチェアを置くとより安心です。
浴槽に浸かる際の姿勢も重要です。浴槽内では、背中をしっかり浴槽の壁につけ、両足を伸ばした状態が基本となります。
ただし、長時間同じ姿勢を保つことは血行不良を招く恐れがあるため、15分程度で姿勢を変えるか、浴槽から出ることをおすすめします。
半身浴を行う場合は、胸の下あたりまでお湯につかり、上半身はタオルなどで保温します。
この姿勢は心臓への負担が少なく、長時間の入浴でも比較的安全です。特に高血圧の方や心臓に不安のある方には、この方法が適しています。
介助者が洗体を行う際の姿勢も忘れてはなりません。
介助者自身が腰を低くし、膝を曲げた状態で作業することで、腰への負担を軽減できます。無理な姿勢で介助を続けると、介助者自身が腰痛などを引き起こす原因となりますので注意しましょう。
最後に、浴槽からの出入りの際は、浴槽の縁に腰掛けた状態から徐々に動くことが安全です。
手すりがあれば積極的に活用し、ゆっくりと慎重に動作を行いましょう。特に浴槽から出る際は体力が消耗している状態なので、より一層の注意が必要です。
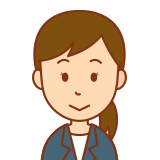
シャワーチェアがあると本当に安心できるわ
在宅介護お風呂介助におすすめの便利グッズ4選

在宅での入浴介助をより安全で負担の少ないものにするためには、適切な介護用品の活用が欠かせません。介護者の負担を軽減し、介護される方の安全と快適さを確保するための便利グッズを紹介します。
それでは、在宅介護のお風呂介助に役立つアイテムを見ていきましょう。
これらのアイテムは、介護保険の福祉用具購入費支給の対象となるものもあります。市区町村の介護保険窓口や担当のケアマネージャーに相談して、制度を有効に活用しましょう。
それでは、各アイテムの特徴や選び方について詳しく説明します。
すべり止めマット
浴室内の転倒防止に最も基本的なアイテムです。
滑りやすい浴室の床に敷くだけで、安全性が格段に向上します。初めて介護用品を導入する方にもおすすめの、費用対効果の高いアイテムです。
すべり止めマットには大きく分けて、浴室床全体に敷くタイプと、浴槽内や出入り口など特定の場所に敷く小型のタイプがあります。
全体に敷くタイプは広範囲をカバーできる利点がありますが、掃除がやや煩雑になる場合もあります。一方、部分的に敷くタイプは必要な場所だけにピンポイントで設置でき、コストも抑えられます。
選ぶ際のポイントは、まず素材です。
天然ゴム製は滑り止め効果が高いですが、劣化が比較的早いことがあります。
シリコン製は耐久性に優れていますが、価格がやや高めです。また、吸盤付きのタイプは固定力が高いですが、床の素材によっては密着しにくい場合もあるため、設置前に確認が必要です。
サイズ選びも重要です。浴室の広さや形状に合わせて、適切なサイズを選びましょう。
特に、浴槽の出入りする場所や立ち位置には必ず設置することをおすすめします。
また、マットの厚みも考慮しましょう。厚すぎると段差になってつまずく原因になり、薄すぎると十分なクッション性が得られません。
お手入れ方法も確認しておきましょう。カビや雑菌の繁殖を防ぐため、使用後は水気を切り、定期的に洗浄する必要があります。
洗浄しやすいタイプや、抗菌・防カビ加工されているものを選ぶと、衛生面でも安心です。
予算は3,000円から10,000円程度が一般的です。介護保険の福祉用具購入費の支給対象にもなっていますので、ケアマネージャーに相談してみるとよいでしょう。
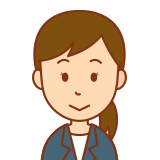
これは最初に買うべき必須アイテムね
シャワーチェア
立ち続けることが難しい方に必須のアイテムです。
座った状態で体を洗うことができるため、介護される方の負担が軽減されるだけでなく、介護者も腰を屈めずに介助ができ、双方にとって大きなメリットがあります。
シャワーチェアには、大きく分けて背もたれのあるタイプとないタイプ、回転機能付きのタイプなど様々な種類があります。
背もたれ付きは長時間の使用でも疲れにくく、特に体力の少ない高齢者や障害のある方に適しています。回転機能付きは浴槽への移動がスムーズにできるため、介護者の負担軽減に効果的です。
選ぶ際の重要なポイントは、まず高さ調整ができるかどうかです。
使用する方の身長に合わせて調整することで、安定した姿勢を保ちやすくなります。足がしっかり床につく高さが理想的です。
また、座面の広さや形状も快適さに直結します。座面が広すぎると浴室内で場所を取りすぎますし、狭すぎると安定感に欠けます。
耐荷重も確認すべき重要な要素です。一般的なシャワーチェアの耐荷重は80kg〜100kg程度ですが、使用者の体重に余裕をもった耐荷重のものを選ぶことをおすすめします。
素材も選択基準の一つです。樹脂製は軽量で持ち運びやすく、錆びる心配もありませんが、耐久性はアルミ製に比べるとやや劣ります。アルミ製は頑丈で安定感がありますが、重量があるため移動には少し力が必要です。
価格は基本的なタイプで8,000円から15,000円程度、回転機能付きなど高機能なタイプになると20,000円から30,000円程度が相場です。
こちらも介護保険の福祉用具購入費の対象となりますので、活用を検討しましょう。
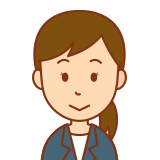
高さ調整できるものが便利だわ
入浴用リフト
浴槽の出入りが困難な方に大きな助けとなります。
介護者だけの力で浴槽への出入りを介助するのは非常に大変であり、双方にとって危険も伴います。入浴用リフトを使用することで、安全かつ負担の少ない入浴が可能になります。
入浴用リフトには主に電動タイプと手動タイプがあります。
電動タイプはボタン操作一つで昇降するため、介護者の負担が最小限に抑えられますが、価格は高めです。
手動タイプはレバーやハンドルで操作するため力が必要ですが、比較的リーズナブルで故障のリスクも低くなっています。
選ぶ際のポイントはまず、浴槽の形状や大きさとの相性です。特に深さや縁の幅によっては設置できないモデルもあるため、事前に浴槽のサイズを測っておくことが重要です。
また、リフトの座面の高さが調整できるかどうかも確認しましょう。適切な高さに調整できることで、浴槽内での安定した姿勢を保つことができます。
防水性能も重要な要素です。
電動タイプの場合、モーター部分が完全防水になっているかどうかを確認しましょう。
また、バッテリー式か電源コード式かによっても使い勝手が変わってきます。バッテリー式は設置場所に制限がありませんが、充電管理が必要です。
コンパクトに収納できるかどうかも考慮すべきポイントです。
使わない時に収納できるものや、取り外しが簡単なものだと、浴室を共有する家族にとっても便利です。特に、浴室のスペースが限られている場合は重要な選択基準となります。
価格帯は手動式で5万円から10万円程度、電動式では15万円から30万円程度が一般的です。
高額ではありますが、介護保険の福祉用具レンタルの対象となるものもあります。必要性が高い場合は、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員に相談してみましょう。
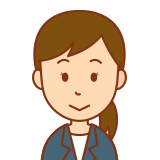
腰への負担が減るから本当に助かるわ
手すりの設置
転倒防止の要となる重要なアイテムです。
浴室内は水で濡れて滑りやすく、最も転倒リスクの高い場所です。適切な位置に手すりを設置することで、安全性が大幅に向上し、自立した入浴をサポートすることができます。
手すりには大きく分けて、工事が必要な固定式と、工事不要の吸盤式があります。
固定式は壁や床にしっかりと固定するため、安定感があり耐久性に優れています。しかし、設置には専門業者による工事が必要で、賃貸住宅では設置できない場合もあります。
吸盤式は工事不要で簡単に取り付けられるメリットがありますが、吸着力の定期的なチェックが必要です。
設置場所の選定も重要です。
まず浴槽の縁に手すりを設置することで、浴槽の出入りがスムーズになります。
また、洗い場に立つ際の支えとなる縦手すり、浴室の出入り口付近の手すりも有効です。使用者の身長や体格、麻痺の状況などに合わせて、適切な高さや位置に設置することが大切です。
固定式手すりの材質は、主にステンレス製、樹脂製、樹脂被覆ステンレス製などがあります。
ステンレス製は耐久性に優れていますが、冬場は冷たく感じることがあります。樹脂製は温かみがありますが、経年劣化で強度が落ちる場合があります。
樹脂被覆ステンレス製は両者のメリットを兼ね備えていますが、価格はやや高めです。
握りやすさも重要なポイントです。直径32mm前後の丸形状が最も握りやすいとされています。
また、表面に凹凸があるなど、濡れた手でも滑りにくい加工がされているものを選ぶと良いでしょう。
吸盤式は5,000円から15,000円程度、固定式は1本あたり10,000円から30,000円程度が相場です。工事費用は別途10,000円から30,000円程度かかります。
手すりも介護保険の福祉用具購入費の対象となりますので、制度を活用するとよいでしょう。
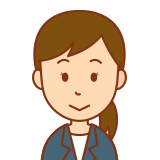
安心感が全然違うものね
介護用入浴着
プライバシーと尊厳を守る配慮のアイテムです。
入浴介助は最もプライバシーに関わる介護の一つです。特に異性間の介護では、お互いの心理的負担を軽減するための工夫が必要になります。
介護用入浴着はそんな悩みを解決する心強い味方となります。
介護用入浴着には、全身タイプ、上半身用、下半身用など様々な種類があります。
全身タイプは体全体をカバーしますが、洗いにくい部分もあります。部分用は必要な箇所だけをカバーできるため、洗体がしやすいというメリットがあります。使用者の状態や好みに合わせて選ぶとよいでしょう。
素材選びも重要です。ナイロンやポリエステルなどの速乾性の高い素材が主流ですが、肌触りや伸縮性も考慮する必要があります。
特に、肌が敏感な方には、綿混の素材や肌当たりの優しい加工がされているものがおすすめです。
着脱のしやすさも確認しましょう。
マジックテープやスナップボタンで開閉できるタイプは、着脱が容易で介助者の負担も軽減されます。また、サイズ調整が可能なものだと、体型の変化にも対応できて長く使えます。
デザインやカラーも選択肢が増えています。単なる機能性だけでなく、おしゃれな印象のものも多く、気分も明るくなります。好みのデザインを選ぶことで、入浴への前向きな気持ちを促すこともできます。
価格は基本的なタイプで3,000円から7,000円程度が一般的です。
耐久性を考えると複数枚用意しておくと、洗濯・乾燥の間も使用できて便利です。
介護保険の対象外ですが、比較的リーズナブルな価格で購入できるため、介護の質を向上させる投資として検討する価値があります。
まとめ 在宅介護のお風呂介助を安全に
今回は、在宅介護のお風呂介助を安全に行うためのコツと役立つグッズについて紹介しました!
- 入念な準備が必須
- 安全な介助手順がある
- 便利グッズが助けになる
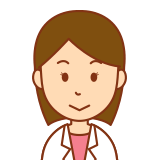
記事に書いてあった便利グッズを取り入れてみたら、お風呂介助がずっと楽になって、毎日の介護の負担が減ったね
お風呂介助は介護者にとって体力的にも精神的にも負担が大きいものですが、正しい知識と適切なサポートグッズを活用すれば、その負担を軽減することができます。
ぜひ試してみてください
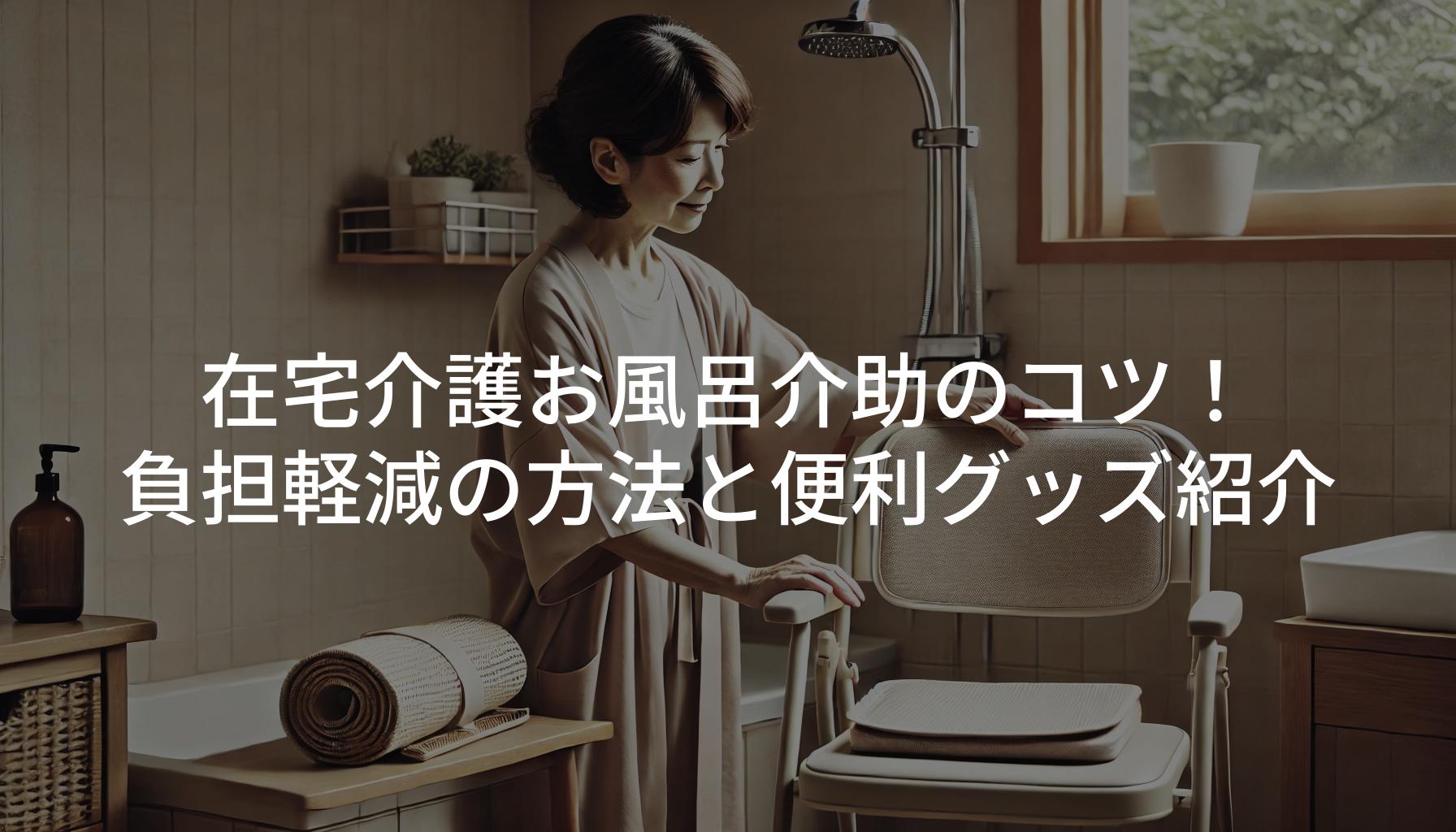
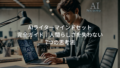
コメント